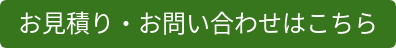今年もオープンキャンパスの季節が近づいてきましたが、集客の準備は順調でしょうか。「昨年と同じでは成果が見込めない」「新しい施策を試したいが、何から手をつければ良いか分からない」といった悩みを抱えている広報担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そうしたお悩みを解決するために、明日からでも始められる具体的な集客施策をオンラインとオフラインの両面から網羅的に解説します。貴校の状況に合った最適なアプローチを見つけ、集客を成功させましょう。
なぜ今、オープンキャンパスの集客が重要なのか?
少子化が進行する現代において、大学や専門学校の学生募集はますます厳しさを増しています。その中で、オープンキャンパスは学校の未来を左右する極めて重要なイベントです。パンフレットやWebサイトだけでは伝わらない、学校の「生」の魅力を高校生や保護者に直接感じてもらうことで、入学への意欲を大きく高めることができます。
少子化による大学間競争の激化
日本の18歳人口は年々減少傾向にあり、多くの学校にとって学生確保は深刻な課題です。日本私立学校振興・共済事業団の調査によると、私立大学の約3割が定員割れという状況にあります。
このような厳しい環境で選ばれる学校になるためには、他校との差別化を図り、自校の魅力を積極的に発信していく必要があります。その最も効果的な場が、オープンキャンパスなのです。
引用元:https://www.shigaku.go.jp/files/shigandoukouH31.pdf?_fsi=AncCFNgG
入学意欲を高める最大の機会
オープンキャンパスは、高校生が進学先を決める上で非常に大きな影響を与えます。
株式会社ディスコの調査では、来校型のオープンキャンパスに参加した高校生の90.3%が「入学意欲が高まった」と回答しています。
実際にキャンパスを訪れ、教員や在学生と交流し、授業や施設を体験することは、Webサイトを眺めるだけでは得られない強い動機付けになります。つまり、集客に成功し、一人でも多くの高校生にキャンパスへ足を運んでもらうことが、そのまま入学志願者の増加に直結するのです。
引用元:https://www.career-tasu.co.jp/press_release/8444/?_fsi=AncCFNgG
→少子化時代の学生募集戦略:大学・専門学校が取るべき施策とは│株式会社荒川印刷
オープンキャンパス集客におけるよくある課題
多くの広報担当者が、集客の重要性を理解しつつも、具体的な施策に頭を悩ませています。ここでは、多くの学校が直面しがちな共通の課題について整理します。
ターゲット層に情報が届かない
「伝えたい魅力はたくさんあるのに、肝心の高校生に情報が届いていない」これは非常によくある課題です。現代の高校生は、テレビや新聞といった従来のマスメディアよりも、SNSや動画プラットフォームを中心に情報を収集しています。
そのため、学校側が発信する情報と、高校生が普段接しているメディアとの間にギャップが生まれてしまいがちです。適切なチャネルでアプローチできていない場合、どんなに良いコンテンツを用意しても見てもらうことすらできません。
競合校との差別化が難しい
多くの学校が同じ時期にオープンキャンパスを開催するため、他校のイベントの中に埋もれてしまうことも少なくありません。模擬授業やキャンパスツアーといった定番のプログラムだけでは、高校生の印象に残りにくくなっています。自校ならではの「強み」や「独自性」を打ち出し、他校にはない特別な体験を提供できるかどうかが、集客成功の鍵を握ります。
魅力的なコンテンツを企画できない
集客がうまくいかない原因は、広報活動だけでなく、オープンキャンパスのプログラム内容そのものにある可能性もあります。参加してくれた高校生や保護者の満足度が低ければ、それがSNSなどを通じてネガティブな口コミとして広がりかねません。「参加者目線で、本当に知りたいこと、体験したいことは何か」を深く掘り下げ、魅力的なコンテンツを企画する力も問われています。
【オンライン編】今すぐ始めるべきオープンキャンパスの集客方法
デジタルネイティブである今の高校生にアプローチするには、オンラインでの施策が不可欠です。ここでは、すぐにでも着手すべきオンラインの集客方法を紹介します。
|
施策名 |
目的 |
主なターゲット |
|
SEO対策 |
学校名や関連キーワードで検索した際に上位表示させ、継続的な流入を確保する |
情報収集を始めたばかりの潜在層から、比較検討中の顕在層まで幅広く |
|
SNS活用 |
日常的に利用するプラットフォームで接触し、親近感を醸成、情報を拡散する |
高校1〜3年生、在学生 |
|
Web広告 |
ターゲットを絞り、オープンキャンパス情報を直接届け、認知拡大と申込を促進する |
特定の地域や興味関心を持つ高校生、保護者 |
|
メールマーケティング |
資料請求者など、すでに関心を持つ層に対し、定期的な情報提供で関係を維持・深化させる |
一度接点を持った入学検討者 |
全ての基本となる学校サイト・ブログの最適化(SEO)
学校の公式サイトや特設ページは、あらゆるオンライン施策の受け皿となる最も重要な場所です。まずは「(地域名) 専門学校」や「(学部名) 大学」といったキーワードで検索された際に、自校のサイトが上位に表示されるようにSEO(検索エンジン最適化)対策を行いましょう。
また、オープンキャンパスの特設ページは、日程、プログラム、申し込みフォームなどの必要情報を1ページに集約し、参加希望者が迷わずに行動できるよう分かりやすく設計することが大切です。
高校生と直接繋がるSNSの戦略的活用
Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、LINEといったSNSは、高校生の生活に深く浸透しており、活用は必須です。各SNSの特性を理解し、例えばInstagramではキャンパスライフが伝わる写真やショート動画を、Xでは最新情報やイベントの告知を、LINE公式アカウントでは登録者へのダイレクトな情報発信を行うなど、使い分けることが効果的です。在学生に登場してもらい、リアルな声を発信することも親近感を持たせる上で有効でしょう。
ターゲットに確実に届けるWeb広告
より能動的にターゲットへアプローチしたい場合は、Web広告を活用します。例えば、特定のエリアに住む高校生や、特定の分野に興味を持つ層に絞って広告を配信することができます。一度サイトを訪れたけれど離脱してしまったユーザーに再度広告を表示する「リターゲティング広告」も、申込を後押しするのに有効な手法です。
入学検討者との関係を深めるメールマーケティング
資料請求や過去のイベント参加などで得たメールアドレスのリストは、貴重な財産です。これらのリストに対して定期的にメールマガジンを配信し、オープンキャンパスの最新情報や、学校の魅力を伝えるコンテンツを届けることで、継続的な関係を築き、参加へと繋げることができます。
【オフライン編】伝統的だが効果的な集客方法
デジタル施策が主流となる中でも、古くからあるオフラインの手法が効果を発揮する場面も多くあります。オンラインと組み合わせることで、より高い相乗効果が期待できます。
|
施策名 |
目的 |
主なターゲット |
|
ダイレクトメール(DM) |
対象者の手元に直接情報を届け、特別感を演出し行動を促す |
資料請求者、高校の進路指導部 |
|
高校訪問 |
進路指導担当教員との信頼関係を構築し、自校の魅力を直接伝えてもらう |
高校の教員、生徒 |
|
ポスター |
地域や校内で視認性を高め、日常的に情報を露出させる |
通学路付近の高校生、保護者、地域住民 |
|
パンフレット |
詳細な情報を手元に残し、熟読・共有を促す |
オープンキャンパス参加検討者、資料請求者 |
|
進学相談会 |
多くの高校生や保護者と直接対話し、認知度向上と一次的な情報提供を行う |
幅広い地域の高校生、保護者 |
開封される工夫を凝らしたダイレクトメール(DM)
ただのチラシを送るのではなく、形状やデザインに工夫を凝らしたユニークなDMは、他の郵便物の中で際立ち、開封率を高めます。例えば、封筒一体型のDMや、特典をわかりやすく記載することで、受け取った高校生の興味を引き、Webサイトへのアクセスやイベント参加のきっかけを作ることができます。
顔の見える信頼を築く高校訪問
進路指導担当の先生との良好な関係は、学生募集において非常に重要です。定期的に高校を訪問し、学校の最新情報や魅力を直接伝えることで、先生方から生徒へ推奨してもらいやすくなります。特に、自校の教育方針や強みを深く理解してもらうことで、単なるパンフレット設置に留まらない、熱意のこもった紹介が期待できます。
目を引くデザインで差別化するポスター掲示
ポスター掲示では、まず通学路沿いや部活動棟前、図書室前といった生徒の行動動線に合った場所を選ぶことが鍵です。デザイン面ではキャッチコピーをシンプルかつインパクトのある一文に絞り、写真やイラストを大きく配置することで視認性を高めます。さらに掲示期間をオープンキャンパス開催日の約三週間前から開始し、開催一週間前には別デザインの新しい訴求文言と差し替えることで注目度を維持できます。
手元に残るパンフレットで深い情報伝達
パンフレットは厚手の用紙やマット加工といった紙質へのこだわりにより高級感と信頼感を演出し、持ち帰ってじっくり読んでもらうための媒体です。冊子タイプにすることで読みやすさを確保し、学校紹介から学部・学科説明、キャンパスライフの実例、在学生の声、参加申し込み方法へと自然にストーリー性をもたせる構成が理想的です。配布は進路指導室や近隣予備校、進学相談会のブースなどで直接手渡しし、開催日の約一か月前から開始すると効果的です。
多くの高校生に会える進学相談会への出展
進学相談会は、進学を考えている多くの高校生や保護者と一度に接点を持てる貴重な機会です。ここでの出会いをきっかけに、後日のオープンキャンパス参加に繋げることが目標となります。ブースの装飾を工夫したり、親しみやすいスタッフが丁寧に対応したりすることで、良い第一印象を与え、次のステップへと繋げましょう。
集客を成功に導く3つのポイント
様々な集客施策を闇雲に行うだけでは、大きな成果は望めません。施策の土台となる重要な3つのポイントを解説します。
来てほしい学生像(ペルソナ)を明確にする
どのような学生に入学してほしいのか、その人物像(ペルソナ)を具体的に描くことが全ての出発点です。住んでいる地域、学力、興味関心、性格などを詳細に設定することで、そのペルソナに「響く」メッセージやコンテンツは何か、どのメディアでアプローチすべきかが明確になります。
参加者の心をつかむ体験型コンテンツを企画する
高校生は「そこでしかできない体験」を求めています。教員や在学生の協力も得ながら、例えば、最先端の設備を使った実験、プロ仕様の機材に触れる体験授業、在学生が案内する「裏側」キャンパスツアーなど、参加者の記憶に残り、SNSでシェアしたくなるような魅力的なプログラムを企画しましょう。
PDCAを回し継続的に改善する
集客施策は一度実施して終わりではありません。各施策からどれくらいのアクセスがあり、何件の申し込みに繋がったのかを必ずデータで計測・分析(Check)します。その結果を基に、「なぜこの広告は効果があったのか」「なぜこのページの離脱率が高いのか」といった改善点を見つけ(Action)、次の施策に活かす(Plan→Do)というPDCAサイクルを回し続けることが、成功への確実な道筋となります。
まとめ
オープンキャンパスの集客は、少子化時代の学校運営において最も重要な課題の一つです。成功のためには、まず来てほしい学生像を明確にし、そのターゲットに響くオンライン・オフラインの施策を組み合わせることが不可欠です。
そして、魅力的なプログラムを企画し、実施後は必ず効果測定と改善を繰り返すPDCAサイクルを徹底することが、継続的な成果へと繋がります。この記事で紹介した手法やポイントが、貴校の学生募集活動の一助となれば幸いです。